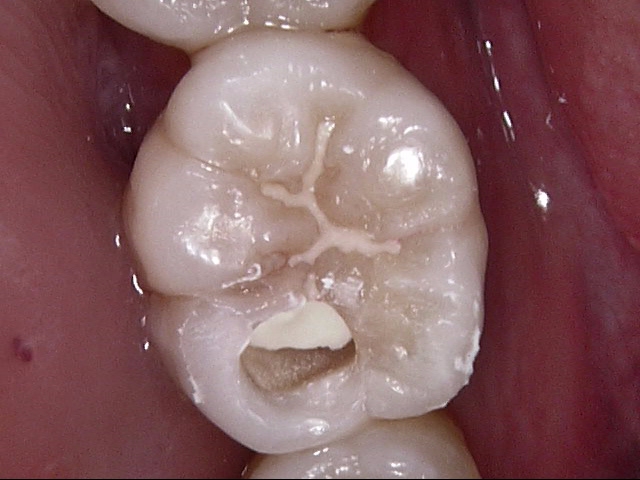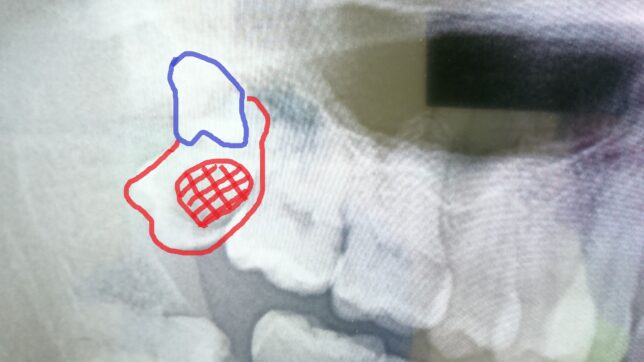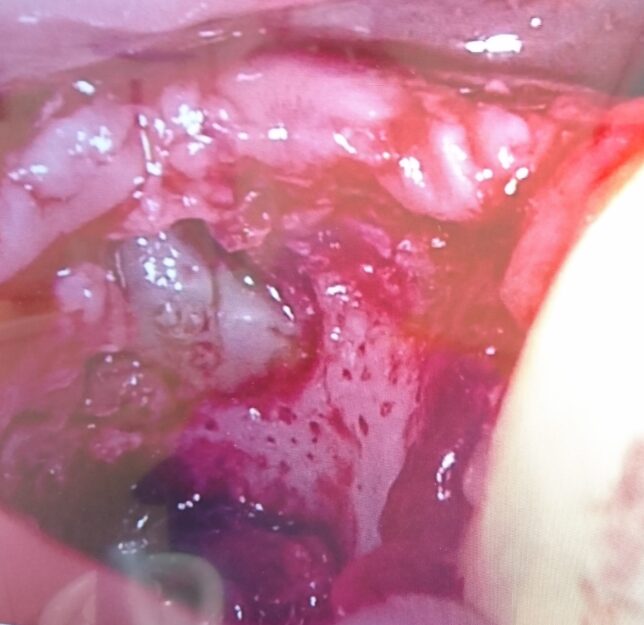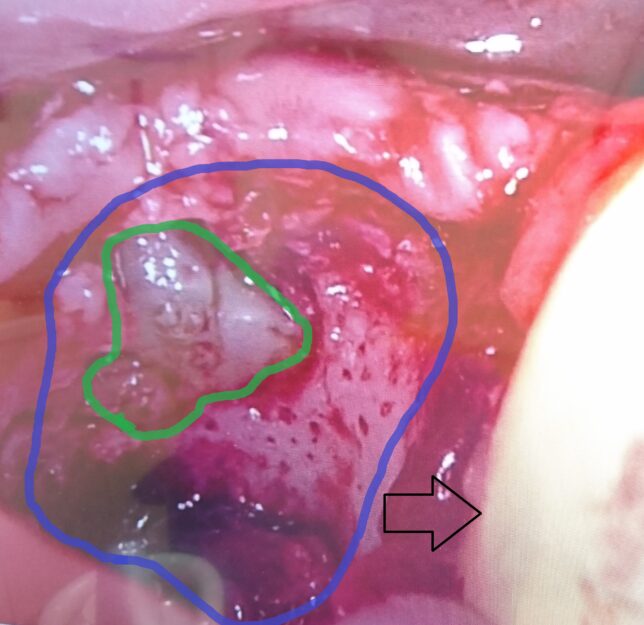院長の笹山です。
年末年始と年明け最初の連休を使ってカルテ整理をおこないました。
カルテの保存期間は法律で5年と決まっており、保存期間を過ぎたカルテは整理していかないと溜まる一方で、医院に保管するスペースが無くなってしまいます。
カルテを整理するなかで、保存期間をとうに過ぎている昔のカルテが入った保管ケースをいくつか発見しました。
飛び飛びですが、平成の初期だったり、古いものでは昭和50年代のものもありました。
カルテというものは治療の記録だけでなく、患者さんの保険証の情報も記載されています。
当院には先代の頃から通われている高齢の患者さんが多くいらっしゃるのですが、その方々が過去にどんなお仕事をしていらしたのかが、カルテの保険証欄を見るとある程度分かります。
「あの方、学校の先生だったんだ。」とか「あの企業にお勤めだったんだ。」「看護師さんだったんだ。」などです。
そんな感じがするなぁと思う方もいらっしゃれば、失礼ながら意外だなと感じる方もいらっしゃいました^^
皆さん仕事を何十年も続けられて、今のお姿があります。おじいちゃん、おばあちゃんの患者さんとしてだけでなく、人生の先輩としての尊敬の気持ちを忘れてはいけないとあらためて感じました。
こんな経験を思い出しました。
私がまだ勤務医だった時、20代の終わりくらいの話です。
勤務先で高齢者の男性患者さんに叱られたことがあります。
「説明が足りない。年寄りだと思って説明をはしょるんじゃない!」
自分では普通に説明したつもりだったのですが、どこかで「おじいちゃんの患者さんだから…細部まで詳しく説明しなくてもいいんじゃないか。」と思っていたのかもしれません。
後で院長先生に「あの患者さんは、昔会社経営をされていて、それなりの立場にあった人だから、そういう接し方は良くない。」と叱られました。
そんなことで、高齢者の方をおじいちゃん、おばあちゃんではなく、人生の先輩として接することの大切さを知りました。
もちろん、おじいちゃんやおばあちゃんとして接したほうが、患者さん自身が楽な場合もありますが、そうでない場合もあるということです。
カルテ整理の話に戻ります。
カルテは大きなみかん箱12箱分くらいを休診日を4日間利用して整理しました。
重さにして何キロでしょう。多分全部合わせて、60キロぐらいあったと思います。整理が終わって、なんとなく医院が軽くなったような気がします。
普段使わない筋肉を使ったので足腰が筋肉痛で2,3日痛みましたが、カルテ整理をして、心も整理された気がします。