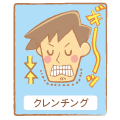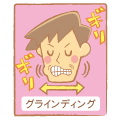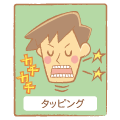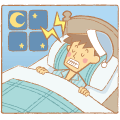院長です。
日々知識と技術の習得に努め、目の前の患者さんに満足して頂ける治療結果を出せるように励んでいます。
今回は総入れ歯について書きます。
総入れ歯とは歯が一本もない人が装着する入れ歯です。
歯が一本もないので部分入れ歯のように残っている歯にバネをかけたりすることはできません。
部分入れ歯
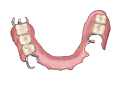
では上あごの総入れ歯はバネをかける歯がなく支えられないのに、どうして外れないのか。
下の図のように上あごの歯茎も覆って、吸盤のように吸い付かせて落ちないようにしています。
総入れ歯
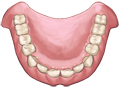
お風呂の壁や台所のシンクに吸盤を付けるようなイメージです。
ただし、入れ歯は入れるだけでなく、食事をするために咬まなければなりませんので、咬む力が加わります。
この時にしっかりと作られていない義歯はその力に負けて吸着がなくなり外れる、もしくは外れそうになります。
吸盤に隙間から空気を入れるとすぐ落下してしまうのと同じです。
会話の時も、上下の歯は当たりますので、その力で会話している時に外れそうになることもあります。
それを防ぐにはどうすればいいか。入れ歯安定剤を塗りつけて使うという方法もありますが、常用すると、かみ合わせが狂ったり、入れ歯が不潔になったりと問題が出てきます。安定剤は一時的なものをお考えいただくのが良いです。
歯のない部分の骨や歯ぐきの状態にもよりますが、入れ歯の型採りやかみ合わせの調整をきちんとおこなえば、安定剤を使わなくても、外れない、外れそうにならない義歯を作ることは可能です。
総入れ歯を安定して咬めるようにするには、知識や技術が大切で、術者によって結果に差がかなり出ます。
毎回の治療ごとに、たくさんのチェックポイントがあり、ひとつづつステップを踏むことが重要で診療時間外の技工作業やシミュレーションが欠かせませんので結構な労力のかかる仕事です。
最近ではめずらしく立て続けに総入れ歯を作ることになり、同時進行で何ケースが治療を始めたのでちょっと大変ですが、
年末のブログに入れ歯の治療を更に充実させると書いたところだったので、良いタイミングでした。
入れ歯作りは歯医者の職人的な部分が発揮される治療ですので、やりがいを感じながら進めています。